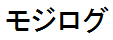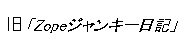3Dのレンダリングをやりはじめて、静物画の面白さがわかった
ウィキペディア - 静物画
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99..
<静物画(せいぶつが)は、西洋画のジャンルの一つで、静止した自然物(花、頭蓋骨、狩りの獲物、貝殻、野菜、果物、台所の魚など)や人工物 (ガラス盃、陶磁器、パン、料理、楽器、パイプ、本など)を対象とする>。

ポール・セザンヌ(1839-1906、フランス)の静物画

ゲオルク・フレーゲル(1566-1638、ドイツ)の静物画
静物画といえば、テーブルの上に皿や果物が置いてあるのを描いたような、地味な絵だ。
これのどこが面白いのか、私はずっとわからなかったのだが、3Dのレンダリングをやりはじめてから、静物画の面白さがわかった気がした。
静物画の主題は、果物などの静物そのものというよりも、むしろ「光」だったのだ。もっといえば、「どう見えるか」ということ、それが主題なのだ。
静物画を描く画家は、果物を描きたいというよりも、その構図や、その光景を成立させている光、「それがどう見えるか」を描きたいのだ。
3DのCGでは、箱や球などがよく配置されているが、これは静物画でいつもリンゴなどが描かれるのと似ている。
3DのCGで箱や球がよく使われるのは、それが組み込みで使えるからというのが大きい理由でもあるが、「箱や球がよく使われてはいるが、箱や球が主題というわけではない」という点で、それは静物画が成立している仕方と似ている。静物画でも、主題はリンゴではないのだ。
静物画でも、3DのCGでも、そこに出てくるリンゴや球といったオブジェクトが主題なのではない。オブジェクトをどう並べて、それをどういう方向から見るか、それでどういう「構図」ができるのか、そこに「光」がどのように走り、ひろがって、それぞれのオブジェクトにどのような色や感触を生み出し、構図全体をわたしたちの眼に対してどういう光景として見せているか。それが主題なのだ。
同じリンゴでも、どのように置かれ、どのようなものに囲まれ、どのような光に照らされるかで、その表情はまったく異なる。静物画が描いているのは、リンゴではなくて、光が生み出すその繊細な世界なのだ。
3Dのレンダリングというものを通じて、大げさにいえば、私は「光というものを見つけた」ような気がしている。それはCGや3Dといった話を超えて、私の「世界認識」に影響を与えている。
光がこれほど重要なものならば、例えばプロフェッショナルな写真の撮影や、映画などの撮影でも、「照明」というものがきわめて重要な役割を果たしていることは間違いない。その世界のプロであれば、そんなことはごくあたり前だろうが、私はこれまで、写真や映画における「照明」というものの役割に、ほとんど注意を払ってこなかった。
そして写真や映画に限らず、ふだんの生活においても、私たちは屋外の光や屋内の光に終始さらされており、その光のもとに周囲を見ている。私たちの目から入ってくる光景は、その光が生み出したものなのだ。
GI(グローバル・イルミネーション)による3Dレンダリングでは、物理法則に基づいて、現実と同じような「光のふるまい」をさせて、画像を生成する。その画像がまるで写真のような「現実感」を持つのは、私たちがふだん目にしているような陰影の感じ、「光のふるまい」がそこにあるからだろう。この「光のふるまい」こそが、おそらく「現実感」の正体なのだ。
関連エントリ:
「現実は光でできている」 グローバル・イルミネーションの威力
http://mojix.org/2009/05/24/reality_light
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99..
<静物画(せいぶつが)は、西洋画のジャンルの一つで、静止した自然物(花、頭蓋骨、狩りの獲物、貝殻、野菜、果物、台所の魚など)や人工物 (ガラス盃、陶磁器、パン、料理、楽器、パイプ、本など)を対象とする>。

ポール・セザンヌ(1839-1906、フランス)の静物画

ゲオルク・フレーゲル(1566-1638、ドイツ)の静物画
静物画といえば、テーブルの上に皿や果物が置いてあるのを描いたような、地味な絵だ。
これのどこが面白いのか、私はずっとわからなかったのだが、3Dのレンダリングをやりはじめてから、静物画の面白さがわかった気がした。
静物画の主題は、果物などの静物そのものというよりも、むしろ「光」だったのだ。もっといえば、「どう見えるか」ということ、それが主題なのだ。
静物画を描く画家は、果物を描きたいというよりも、その構図や、その光景を成立させている光、「それがどう見えるか」を描きたいのだ。
3DのCGでは、箱や球などがよく配置されているが、これは静物画でいつもリンゴなどが描かれるのと似ている。
3DのCGで箱や球がよく使われるのは、それが組み込みで使えるからというのが大きい理由でもあるが、「箱や球がよく使われてはいるが、箱や球が主題というわけではない」という点で、それは静物画が成立している仕方と似ている。静物画でも、主題はリンゴではないのだ。
静物画でも、3DのCGでも、そこに出てくるリンゴや球といったオブジェクトが主題なのではない。オブジェクトをどう並べて、それをどういう方向から見るか、それでどういう「構図」ができるのか、そこに「光」がどのように走り、ひろがって、それぞれのオブジェクトにどのような色や感触を生み出し、構図全体をわたしたちの眼に対してどういう光景として見せているか。それが主題なのだ。
同じリンゴでも、どのように置かれ、どのようなものに囲まれ、どのような光に照らされるかで、その表情はまったく異なる。静物画が描いているのは、リンゴではなくて、光が生み出すその繊細な世界なのだ。
3Dのレンダリングというものを通じて、大げさにいえば、私は「光というものを見つけた」ような気がしている。それはCGや3Dといった話を超えて、私の「世界認識」に影響を与えている。
光がこれほど重要なものならば、例えばプロフェッショナルな写真の撮影や、映画などの撮影でも、「照明」というものがきわめて重要な役割を果たしていることは間違いない。その世界のプロであれば、そんなことはごくあたり前だろうが、私はこれまで、写真や映画における「照明」というものの役割に、ほとんど注意を払ってこなかった。
そして写真や映画に限らず、ふだんの生活においても、私たちは屋外の光や屋内の光に終始さらされており、その光のもとに周囲を見ている。私たちの目から入ってくる光景は、その光が生み出したものなのだ。
GI(グローバル・イルミネーション)による3Dレンダリングでは、物理法則に基づいて、現実と同じような「光のふるまい」をさせて、画像を生成する。その画像がまるで写真のような「現実感」を持つのは、私たちがふだん目にしているような陰影の感じ、「光のふるまい」がそこにあるからだろう。この「光のふるまい」こそが、おそらく「現実感」の正体なのだ。
関連エントリ:
「現実は光でできている」 グローバル・イルミネーションの威力
http://mojix.org/2009/05/24/reality_light
 mojix.org
mojix.org